 01-コラム
01-コラム 天地を相手に生きる
藤平光一先生は「天地を相手に生きる」ことを大切に説きました。私たちは、自分自身の経験に基づき、様々な価値観を持っています。勿論、それは必要なものではありますが、自分の「物差し」なので、物差しそのものがズレてしまうと大変なことになります。しか...
 01-コラム
01-コラム 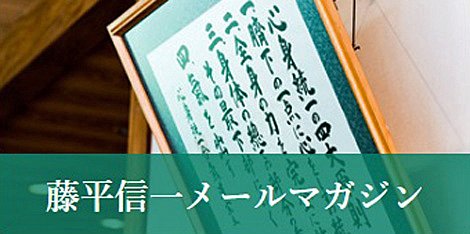 01-コラム
01-コラム 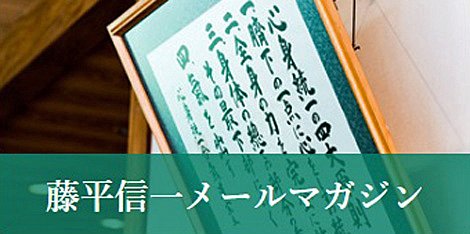 01-コラム
01-コラム 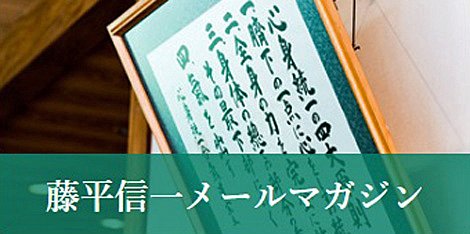 01-コラム
01-コラム 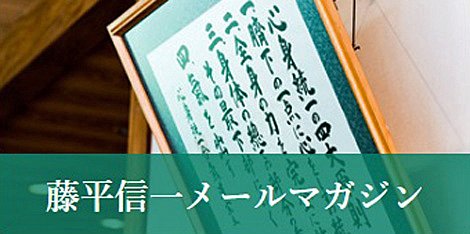 01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム  01-コラム
01-コラム