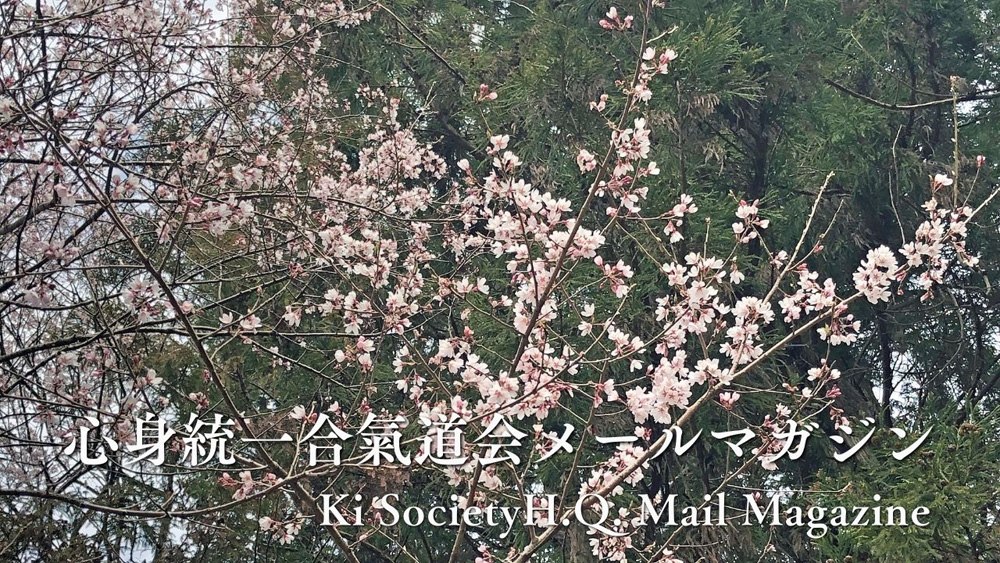人にはそれぞれ重要な転機があります。
「身につける」ことにおいて、私にとっての最大の転機は内弟子時代にありました。
私は継承者を目指していましたので、通常は10年の修行期間が短く設定されて、3年を年限として資質を見極めることになりました。その時点で芽が出なければ諦める約束でした。
3年という期間は日数にすると約1,000日、一日たりとも無駄に出来ません。日々、お供の機会を頂いていたので、藤平光一先生の技を一番近くで、目を皿のようにして学んでいました。
あるとき、藤平光一先生から稽古後に思いがけない言葉をかけられました。
「お前は儂(わし)の一番近くにいるのに、儂のことを何もみていないようだね。今のままでは何年修行しても同じことだよ」
真剣に学んでいるのに「何もみていない」と言われて、私は当惑するばかりでした。納得はできませんでしたが、言葉の意味を理解したいと思いました。
転機は突然に訪れました。
指導者が参加する稽古で、私は相手とぶつかって投げることができませんでした。それを見た藤平光一先生が、「お前にとって、目の前にいる相手はどんな存在だ?」と私に尋ました。
頭では分かっていました。目の前の相手は投げる対象ではなく、一体となって動く人であり、自分と相手の間で境界を設けなければ、ぶつかることなく導ける。
そこでハッとしました。なぜなら、実際の私の「あり方」は違っていたからです。本当のところは「投げる相手」として捉えていて、自分の思い通りに動かしたかったのです。
私は技の形や動きなど「やり方」ばかりを一生懸命に見ていて、「どういう心の状態で技をしているか」という観点では全くみていませんでした。
「あり方」に目がいくようになると、藤平光一先生は道場の中だけではなく、日常生活でも同じように人に接していることに氣がつきました。
相手を無理に動かすようなことはせず、常に一緒に物事を行う姿勢でした。「自分と相手」という境界を引かない「一体である」というあり方だったのです。
そのあり方が「氣」を通じて相手に伝わることで、無意識の抵抗は生じず、ぶつかることなく自在に導き投げていることを理解しました。そして、体得するには日常での実践こそ重要であることも分かりました。
私は「やり方」ばかりを学んでいて、「あり方」をみていませんでした。
あり方という土台があるから、その上にやり方を乗せることができます。やり方ばかり学んでも、あり方がなければ身につくはずがなかったのです。
情報社会の現代においては、「師弟関係で学ぶ意義」が問われています。
わざわざ面倒な人間関係に身をおいて、何年もかけて修行などしなくても、インターネットから情報を得られるから無意味に見えるのでしょう。
「やり方」においては確かにそうです。同じ内容であれば、誰から(何から)学んでも同じことです。やり方は短期間で効果的に学習すべきで、徒に時間をかけても意味はありません。
「あり方」は人から人へ伝わるもので、誰から学ぶかが最も重要です。日常の一挙手一投足から感じ取るもので、だからこそ、師匠と同じ時間を共にすることが大事だったのです。
内弟子修行という仕組みは、そのためにあったのだと思います。それなのに私は当初、内弟子修行でやり方ばかりを見ていたのですから、「何もみていない」と言われるのも当然です。
より大きな視点で見れば、やり方を受け継ぐだけでは継承したことにはなりません。やり方が同じでも、あり方が異なれば「似て非なるもの」に変質してしまいます。
時代の変化や技術の革新によって「やり方」は柔軟に変化していくものですが、「あり方」は常に変わらず、それを受け継ぐことが継承だと私は考えています。
「あり方」という原点に立ち返ることを、私は大切にしています。