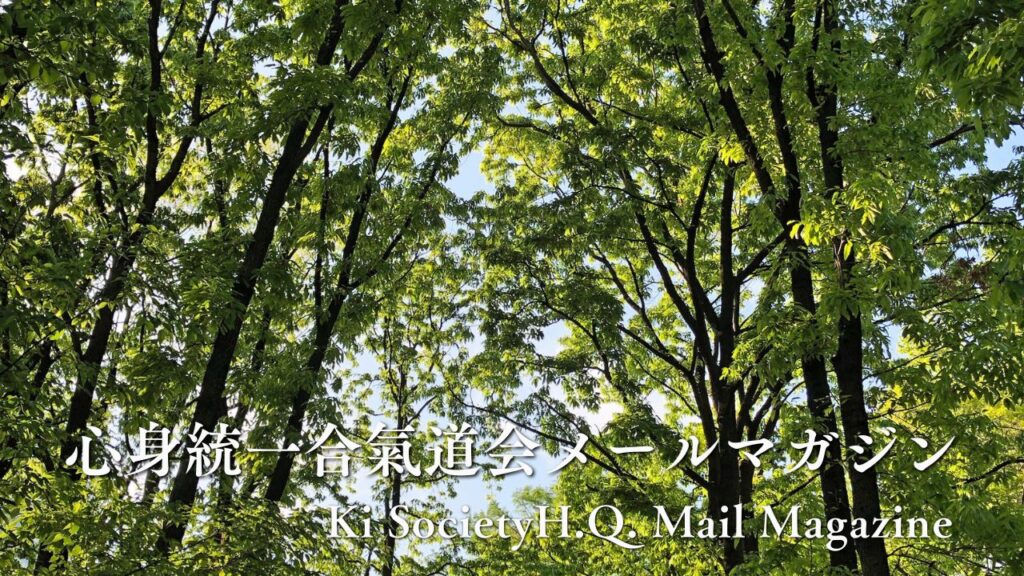
「やばい」
てっきり最近の言葉だと思っていましたが、語源を調べてみると、江戸時代に用いられていた「やば」から派生したようです。「やば」とは「不都合なこと。けしからぬこと。奇怪なこと」、後になって「極めて程度が良いさま」を表す意味が加わったようです。
美味しく感じても「やばい」、不味く感じても「やばい」。
幸運に恵まれても「やばい」、窮地に陥っても「やばい」。
便利な言葉かもしれませんが、異なる状態なのに同じ表現しかできなくなると、心の働きを正しく把握する力が衰えていきます。まるで解像度の低い映像を見るように、自分の心の状態がよく分からなくなってしまうのです。
「嬉しい」という感情にもどこか寂しさがあるとか、「悲しい」という感情にもどこかホッとしているとか、微細な心の働きを認識できなくなります。
心の働きを具体的に表現することによって、解像度は高くなり、自分の心の働きがよく分かるようになります。すると、「なぜそう感じるのか」にアプローチできるようになるので、自身に生じる様々な心の働きを処することができます。
指導者になって間もない頃、私は、ここ一番の場面で不安な気持ちに陥ることがありました。
自分では「なぜ不安が生じるか」が分からなかったので、不安はさらに大きな不安を呼び起こしていました。そうなると自分ではどうすることもできず、あまりに苦しかったので、せめて生じている感覚を書き出して整理することにしました。
頭の中がモヤッとして同じところをグルグルと巡っている感じ。首や肩がこわばっていて、停滞している感じ。何より「臍下の一点に心を静める」ことを学んでいるはずなのに、実際のところ心は乱れている。そんな状態で物事がうまく運ぶはずがありません。
いま自分に生じている感覚は、いったい何なのだろうか。なぜ生じているのだろうか。氣の呼吸法をしっかり行って、心が静まっていくうちに、ふと気がつきました。
「ああ、本当は怖いのか。だから身体が反応しているのか」
当時の私は、失敗して周囲からの評価を失うことが怖かったのです。しかし、無意識のうちに頭で否定していたのでした。評価を失う怖さは本能的なものなので、消し去ることは難しい。しかし、「内向き」になっている心を「外向き」に変えることはできます。
怖く感じること自体は否定せず、達成のためになすべきことに心を向けた瞬間、漠然とした不安は小さくなっていきました。自分で処することができないから不安になるわけで、不安を解消するには、まず自分の状態を正しく知ることであったのです。
大事な場面ですごく固くなってしまうとしましょう。過度に緊張しているときは自分の状態を把握できません。すると、その緊張は自分で処することができない「厄介もの」になります。
自分が緊張していることを自覚すれば、なぜ緊張が生じるのか、どうしたら緊張を乗り越えられるかに取り組むことができます。こうなると不安は相対的に小さくなっていきます。
それでは、どうしたら自分の状態を正しく把握できるでしょうか。
おすすめの方法の一つは、自分の心の働きを具体的に表現することです。ただし、「やばい」といった言葉で片付けてはいけません。具体的に表現できるということは、自分の状態を理解できるということ。心の働きを正しく把握できるということです。
これは、心身統一合氣道の稽古においても不可欠な取り組みです。力が入っていることを自覚し、なぜ力が入るのか心の働きを理解するから、正しく力を抜くことができます。
自分のことを知る。最も基本にして、最も難しいとされることですが、それは、自分の状態を具体的に表現することで磨かれるのです。



